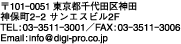| 各紙の紹介・批評
【読売新聞】 4年間にわたるシベリア抑留を生き延びた著者は、帰国後25年を経て、その体験を絵にした。若いころペン画を学んだというが、プロの画家ではない。明石から大阪まで、往復4時間の通勤電車の中で、7年間にわたって描きためた絵は、全部で1000点あまり。本書にはそのうち352点が、詳細な記録文(手記)とともに収録されている。恨みや怒りではなく 何気なくこの本を手に取り、ぱらぱらとぺージをめくったときの衝撃を忘れることが できない。画材は黒ボールペンのみであるにもかかわらず、描かれたあらゆる事物が、たしかな重量感をもって眼前に迫ってきた。シベリアの土と雪、アカマツの幹のざらざらした木肌、俘虜たちが手にした斧の刃、橇を引く馬……。驚嘆すべき記憶力によって、すべてが細部まで克明に再現されている。 シベリア抑留体験を描いた画家は有名無名を問わず数多いが、著者の特徴は「正確に描く」ということへの執着だろう。絵の中に心象風景を一切持ち込まず、日々の生活をひたすらリアリズムに徹して描いている。これほど鮮明に細部を記憶しているのは、そして それを再現することに情熱を傾けたのは、いかに過酷であろうとも、シベリアでの日々が、著者にとってかけがえのない人生の時間だったからに違いない。それを「なかったこと」にしたくはないという強い思いが伝わってくる。 収容所での生活を「極寒と飢餓の地獄」としながらも、「極限の環境に生きる仲間達の姿は美の極致であった」と著者は書く。恨みや怒り、告発のためではなく、人間の生きる姿を記録するために、これらの絵は描かれた。ぺージをめくるたびに、そのことがひしひしと感じられて、胸が熱くなった。 【読売新聞 よみうり寸評】 二人のシベリア抑留体験者の本の出版記念会が今週、東京であった◆山下静夫さん(89)は、4年にわたる過酷な収容所体験を、350枚の細密なペン画と記録文で「シベリア抑留1450日」に著した◆村山常雄さん(81)は、抑留中に死亡した日本人のうち4万6300人分の名簿を「シベリアに逝きし人々を刻す」と題し出版した。うち3万2千人余は独自に集めた資料を基に、漢字に改めた◆山下さんは「戦争なんて二度とごめんだ。そう訴えたかった」とあいさつ。村山さんはロシア語と日本語で歌をうたった。「全国の図書館に置いてもらい、抑留で無残に命を奪われた人たちのことを考えてほしい」◆会場には平均年齢85歳を超す抑留体験者、遺族らが詰めかけ、二人の功績をたたえた。女優の松島トモ子さんもマイクを握る。父親は、松島さんが生まれる少し前に出征し、抑留先で亡くなった◆「山下さんの絵に父の収容所を思い、涙しました。村山さんの名簿に父の名を探しましたが…」。多くの抑留関係者が、同じように2冊の労作と向き合うのだろう。 【毎日新聞】 1918年生まれの著者は旧日本軍の主計軍曹として満州で敗戦を迎え、ソ連に4年間抑留された。少年時より独習したペン画352枚と手記で、その生活を再現したのが本書。「現場でシャッターを切った写真のよう」な画は、帰還後の74〜81年、通勤列車内で描いたという。 粗悪な幕舎での夕食中、食器をつかんだままうなだれる青年の姿。飢餓と重労働に力尽き、息を引き取っていた。「魂はもう日本に帰ってしまったか」。文章は、あえて淡々とつづられる。巨人・水原茂との出会いやロシア人との触れ合いなど、喜怒哀楽を忘れない暮らしぶりに、人間の尊厳が浮かび上がる。 「憎むべきは人ではなく戦争」。戦後62年目に出た証言を、若い世代は重く受け止めたい。 【毎日新聞 大阪】 旧日本兵捕虜としてシベリアで強制労働に従事した4年間を、352点もの精緻なペン画と文章で再現した画文集「シベリア抑留1450日」がこの夏、出版された。作者は兵庫県明石市大久保町江井島の山下静夫さん(89)。極度の寒さと飢えにさらされながらも、ロシア語の「ダモイ」(家へ)を夢見て生き抜いた日本人たちの貴重な記録となっている。 シベリア抑留はへ終戦間際のソ連参戦によって生じた戦後の悲劇だ。旧満州(現中国東北部)の佳木斯に駐屯していた山下さんらは、1945年8月20日にソ連の捕虜となり、シベリア鉄道でイルクーツク近くの収容所に送られた。本では、連行の際にソ連兵が「ダモイ」と言って日本兵を安心させた様子が何度も出てくる。 氷点下50度を超す収容所での肉体労働は、過酷を極めた。飢えによる栄養失調で、夕食中にサジをくわえたまま息を引き取った兵もいた。「極限状態の中(山下さんは旧日本軍の上官について「部下を日本へ無事帰さなければその責任は解除されない」はずなのに、食糧のピンはねや私刑が横行していたとして「日本人が日本人を殺す原動力となったことは否めない事実」と告発している。 49年9月に帰国した山下さんは73年ごろから抑留生活の記憶を文章にしも次いでボールペンでケント紙に個々の場面を克明に描き続けた。「戦争は無駄の最たるもの」との思いからだった。 ロシア語翻訳者の長勢了治さん(57)は「抑留者の本は一般に被害者意識に傾きがちだが、山下さんは驚異的な記憶力でありのままを描いている。その徹底したリアリズムが客観性を獲得している」と話している。 【信濃毎日新聞】 「本当のシベリア」伝えたい約400枚の「抑留画」と、ノート230ページ余に及ぶ手記。敗戦後、シベリアに4年問、抑留された山下静夫さん(89)=兵庫県明石市=が克明に再現した記憶が、大冊の画文集「シベリア抑留1450日」にまとまった。細密なペン画と文から立ちあがってくる、抑留の実態を伝えようとする執念。そこには、旧日本軍の体質が、抑留生活の中で日本人自ら犠牲を増やす結果につながった―という痛恨の思いも込められている。 画文集は、1945年8月9日、満州(現中国東北部)へのソ連軍侵攻の報の記述から始まる。山下さんはそのとき、陸軍輜重兵134連隊本部の主計軍曹として、ソ連国境に近い佳木斯(チャムス)の駐屯地にいた。 17日に敗戦を知り、その後、ソ連軍に武装解除された日本兵たちは、捕虜としてシベリアヘ送られる。北緯56度のイルクーツク州タイシェトにある強制収容所(ラーゲリ)へ着いたのは12月4日。零下55度の極寒の中、森林伐採や鉄道建設の強制労働をさせられた。 一週間ほどした「12月10日ころ」の日付が入った抑留画は、昼食抜きで作業をした後、暖房用の薪(たきぎ)採りに行った兵士が、薪を拾う姿勢で雪の中に倒れ、凍死した姿が描かれている。 夕食の最中、さじを手にしたまま死んだ兵士もいた。栄養失調だった。山下さんは夜明けまで、遺体が凍らないようペチ力の前で暖めた。絵の余白にはこう書かれている。「他人事ではなく明日はわが身であった」 敗戦後、旧日本軍兵士ら60万人がシベリアに抑留され、その一割にあたる約6万人が死亡したとされる。日本の降伏、武装解除後に捕虜として拉致し、強制労働をさせたソ連の行為は、明らかな国際法違反だった。 ただ、山下さんは、抑留の過酷な実態を写し取りつつ、極限状況の下であらわになった日本軍の体質を見つめ、自問を重ねる。 敗戦直後、45年8月30日の記述には、「敗戦を知らない? まだ戦う友軍が」と見出しが付いている。武装解除され牡丹江へ向かう途中だった山下さんたちはその日、ソ連軍と戦闘を続ける日本兵に会う。投降を説得したが、彼らは応じなかった。 「生きて虜囚の辱めを受けず」の戦陣訓の下、捕虜になるより死を選ぶことを教育されてきた日本兵は「捕虜の権利」など知るはずもなかった。そのためラーゲリでの不当な処遇にも従順で、犠牲者を増やす結果となった。ソ連兵は、服従しないドイツ人捕虜と比べ「日本人はよい人間だ」と“評価”した。山下さんは書く。「我々はお人好しの馬鹿だ」 上官風を吹かせて下級兵に私刑を加える上官や、下級兵の食事を減らし、自分が余分に食べる上官もいた。「日本の軍隊は、天皇の名に於て威張り散らす小人物の軍人を大量に生産していて、序列による命令と服従の関係は異国の抑圧生活の中で、日本人が日本人を殺す原動力となった」と山下さんは記す。 4年の抑留の後、山下さんは49年9月に復員した。だが、その後四半世紀、シベリアのことは胸にしまいこんできた。記憶が呼び起こされたのは74年。全国紙が募集した抑留体験者の手記を目にしたときだ。1位に選ばれたのは、入院していた人の体験記だった。 「本当のシベリアはそんなもんじゃない。毎日、生きていられるかどうかも分からなかった」。突き動かされるように、10カ月かかって手記を書きあげ、続けて抑留画を描いた。戦後生まれの息子に伝えたいとの思いから。独習したペン画で、通勤の往復4時間の電車の中で7年間描き続けた絵は、下書きを含め約1000枚になった。 「描きながら涙を流していた」と山下さんは語る。どこの誰かも覚えていない、でも、故郷へ帰る日を語り合いながら夢を果たせず無残に亡くなっていった仲間たち。その姿が、絵の中にあった。 山下さんは言う。「戦争こそ、残酷で、無駄の最たるもの。平和のためであっても、戦争をしてはだめなんだ」 絵の一部を山下さんは83年に私家版で出版。昨年出Lた日露対訳版の印刷を請け負った東京の印刷会社「デジプロ」の編集者・斎藤安弘さん(72)が、残りの絵と手記の存在を知り、画文集の出版に動いた。出版元探しが難航したが、同社代表で斎藤さんの妻セツ子さん(61)が「採算は度外視して後世に残そう」と決断。大手出版社OBらが無報酬で編集に協力し、出版が実現した。 A5判、595ページ。2940円。若い世代を意識して、詳細な見出しを付け、巻末に抑留問題の解説を収めた。 【産経新聞】 兵庫県明石市のシベリア抑留体験者、山下静夫さん(89)が、自身の体験をつづった画文集「シベリア抑留1450日」(東京堂出版)を出版した。350枚の細密なペン画と詳細な回想から伝わってくるのは、平和を希求する透明な詩情である。「自分の画文集を、憎しみを増幅する道具にしたくなかった」と山下さんは話す。「きっかけは、ある新聞が読者から募集した『収容所とは』という手記でした。1席となったシベリア抑留記が、あまりにも軽く書かれていたのです」 これに猛反発した山下さんは、10カ月をかけて体験記を書き上げた。抑留から帰国して25年がたっていたが、記憶は鮮明だった。 「あれほど特異な体験は、忘れようがありません。戦争を知らない息子に自分の体験を伝えたいという思いも強かった」 体験記をつづるうちに挿絵をつけようと思い立つ。片道2時間の通勤電車を書斎に、ケント紙に黒のボールペンで、記憶に深く刻まれた場面を描き始め、8年をかけておよそ1OOO枚の絵を描き上げた。 昭和20年8月15日に戦争は終わらなかった。ソ連は8月8日、日ソ中立条約を一方的に破棄して宣戦布告、9日に満州、南樺太に、18日には千島列島最北の占守島に侵攻、9月5日までに北方四島の占領を完了した。そして武装解除した満州(現中国東北地区)などの日本兵60万人(100万人という説もある)を捕虜としてシベリアに送り、、強制労働に従事させた。抑留中に死亡したのは6万人とも10万人ともいわれるが、その実数はいまだ明確になっていない。 満州・佳木斯(チャムス)の陸軍駐屯地に主計軍曹として勤務していた山下さんは、11月23且に「ダモイ(帰国)」と言われて貨車に詰め込まれ、バイカル湖の北西、タイシェト地区ネーヴェリスカヤの収容所に送られた。途中ハバロフスクでは、「ヤポンスキー、サムライ!」という罵声とともに投石が貨車に浴びせられた。ネーヴェリスカヤに着いたのは12月4日のこと。北満州でも経験したことのない氷点下50度という極寒の中で、飢えに耐えながらの重労働が待っていた。山下さん、27歳。神戸に残した妻子は戦災で亡くなっていた。 「最初の冬は、自然の猛威と過酷な労働の重圧で、明日一日命がもつだろうか、という思いで過ごしていました」 山下さんの4年にわたる抑留生活の回想は、過酷な労働の日々にとどまらず、美しいシベリアの大地、ロシア人との心温まる交流、さらには収容所の中で進められた「民主運動」にも及ぶ。特に印象的なのは、帰国が決まりマーヤという少女に別れを告げる場面だ。 《部屋はうす暗かった。その中にこちらを向いて微笑みながら立っているマーヤの顔が今日は殊の外美しく、まぶしい程に見え、風邪で心なしかやつれたように見える姿が、一層化粧気のない顔を引き立てているように見えた》 折々にはさまれたこうした記述が、えも言われぬ詩情をこの画文集に与えている。 「抑留は地獄のような体験でした。その事実はきちんと伝えたい。でもソ連やロシア人に対して憎悪をぶちまけることはしたくありませんでした。憎むべきは戦争そのものなのです」 【東京新聞】 シベリア抑留、封印の記憶解き…終戦直後、ソ連軍によって大勢の旧日本軍将兵らがシベリアに強制連行された。その「極寒と飢えの地獄」を知ってもらおうと・元抑留者の山下静夫さん(89)=兵庫県明石市=がこの夏、画文集「シベリア抑留1450日」(東京堂出版)を出版した。 「こんな所で死ねるもんか、という思いだけだったな」。山下さんは、自宅の書斎の机で約30年前に描いたボールペン画を手に取ってつぶやいた。細かい線で丁寧に描かれた絵は色あせず、シベリアでの過酷な日々を生々しく訴えかける。 1945(昭和20)年8月、27歳の山下さんは旧満州(中国東北部)で主計軍曹として終戦を迎え、ソ連軍の捕虜に。同年12月、シベリアの収容所に送り込まれた。真冬は零下55度にもなる猛烈な寒さの中、鉄道建設の重蛍働に4年間耐えた。 49年9月に帰国できたが、ソ連帰りという理由だけで共産主義者と決めつけられ、就職にも苦しんだ。だから「シベリアのことは絶対に話すまい」と、長い間口を閉ざしていた。 転機は25年後の74年。ある新聞が公募したシベリア抑留の体験記で1位に当選した手記を読んだときだ。「病院での入院生活ばかり書かれていて、あまりにも軽い印象を受けた」。封印していた記憶を一気に解き放ち、10カ月でリポート用紙260枚の手記を書き上げた。 もともと絵描きが趣味の山下さんは、手記に挿絵をつけたくなった。明石の住まいから勤め先の大阪までの往復4時間の電車内がアトリエ。画材道具はB6サイズ(縦18.2センチ、横12.8センチ)のケント紙に黒のボールペンだった。 きゃしゃな体にこたえた大木の伐採と運搬作業、凍死した仲闇の悲劇、ひもじい収容所生活…。最初の一年半は「毎日が『明日生きていられるか』と思っていた」ほど特に悲惨だった。 ロシア人の上官と結託した日本人捕虜が、ただでさえ少ない食糧を搾取。それを知った山下さんが上官に直訴すると、昼夜休みなく重労働を課せられ、重い肺炎を患った。一週間、ベッドで生死の境をさまよった。 脳裏にあるフィルムを一枚一枚印画紙に焼き付けるように夢中でペンを走らせ、400枚を7年余りで描き切った。これらの手記と絵が今回初めて画文集にまとめられた。 今はせき髄を痛め、絵を描くことから遠ざかっている山下さんが静かに話す。「私の絵を見て、シベリアで私たちが経験したことを知ってほしい。そして戦争は終わった後も残酷だということを感じてほしい」 【北海道新聞】 兵庫県明石市の画家山下静夫さん(89)が、4年間のシベリア抑留生活をつづった画文集「シベリア抑留1450日」(東京堂出版)を刊行した。抑留生活の手記に約350枚のペン画を添えた600ページの大作で、翻訳作品に山下さんの挿絵を使うなど交流の深い上川管内美瑛町の翻訳家長勢了治さん(57)が解説を担当している。山下さんは1945年、旧ソ連との国境に近い旧満州(現中国東北地方)のチャムスの駐屯地に主計軍曹として勤務し、戦後、捕虜となってバイカル湖西方のタイシェトの収容所へ運ばれた。著作では同年8月9日の旧ソ連軍侵攻から、京都府舞鶴市に復員した49年までを描いている。 74年、全国紙に掲載された抑留体験記を目にし「本当のシベリアはそんなものではない」と10カ月で手記を執筆。さらに勤め先に通う電車の中で記憶の中のシベリアをペン画で描き、7年で約400枚を書き上げた。このうち200枚は83年に私家版で発刊。昨年6月にも日ロ対訳版の画集「シベリヤの物語」(刊行委員会)で発表した。 新作では未発表の手記とペン画約150枚をまとめた。林の中でまきを探しながら亡くなった仲間や脱走兵の悲惨な最期を悼む一方で、シベリアの自然や動物、ロシア人との交流なども描き、淡々とした筆致が特徴だ。 山下さんは「シベリアでは毎日命がけの日々だった。しかし正確に記録したいと、極力感情を抑えて書いた」と話す。前作の翻訳を担当するなど交流が深く、解説を書いた長勢さんは「リアリズムが貫かれている。若い人にも読んでほしい」と話している。 【熊本日日新聞】 戦後六十二年、この夏、俘虜としてシベリア抑留体験を持つ二人の元兵士による著書が続けて発刊された。画文集『シベリア抑留1450日』山下静夫著。著者は1918(大正7)年神戸市生まれ、敗戦時27歳。関東軍主計軍曹。出征中に内地に残した長男と妻を病で亡くしている。4年の抑留を経て帰国、再婚後生まれた息子に、戦争を伝えたくてこの本の出版を決めたという。 絵は、ボールペンによる白黒の細密画。とにかく「カク」ことが好きで14歳のころからペン画を独習、「カクモノ」を取リあげられた苛酷な俘虜生活の中でも、風景や労働する姿の「美しさ」は深く心に刻んだという。それでも抑留4年目ともなると、いわゆる民主運動のために、プラカードや、レーニン、スターリンの肖像画も描かされ、特技を生かすことになったことも記されている。 「1945 8・9」に始まリ、49年9月、ナホトカを経て舞鶴港に上陸、一時入院となる日までの352点の挿入画は写実そのもので、日付を伴う手書きの文章も添えられ、説得力のある記録となっている。 62年前の8月9日、ソ連軍侵攻時の関東軍輜重隊上級下士官としての緊迫した会議の場面から中国人捕虜の解放、軍に置き去リにされる開拓団難民など…。玉音放送、武装解除、屍臭の中の敗残の列。そして極寒の地ソ違邦イルクーツク州タイセットのラーゲリヘ。バム鉄道建設の苛酷な虜囚の日々「1450日」の生と死。憎しみを超えたロシア人との交歓もある。帰国後、事情もあってすぐにではなく、心に刻んだ虜囚の日々をペン画にしたのは、通勤電車の中であったとは驚く。その数、1000枚とも…。「カクコトガスキ」とはいうものの常人でできることでは無い。 もうすぐ90歳になる著者は言う。「仇は仇を呼ぶ、最も憎むべきは戦争。平和を守ることこそ戦争経験者のつとめ…」。その言葉は、重い。 『シベリアに逝きし人々を刻す』村山常雄編著。重厚そのものの本が私に届いたのは7月で知遇を得て、日本海を臨む豪雪の地、新潟・糸魚川に著者を訪ねたのは昨年2月、穏やかな中に不屈なものを秘めたその北陸の風貌が重なリ、その達成をよろこんだ。 62年前の、敗れはしても戦争は終わった。戦場に生き残った兵は、殆どが軍隊の樫楮から解放され、故国への帰還を望み、信じた。 しかし、満州での現実は、スターリン体制下のソ運邦に捕虜として連行され、強制労働の悲哀に沈むことになった。その総ては、先の山下氏の画文集のとおリであリ、生還を果たせずに6万ともいわれる死者が、いまも凍土に眠リ続けている。 元抑留者の一人である私は、先年、再び訪ねることは無いと思っていたあのシベリアを旅した。そして、僅かに残るラーゲリの痕跡を確かめ、白樺林に消えかかる死者の土まんじゅうにも出会った。中でも、遺骨収集の跡とされる枯草に沈む方形の穴には、骨の残欠もあると案内のロシア人は言う。その見えない骨庁に、彷僅る魂の働突を聴く思いがして、私はただ手を合れせるしか無かった。 編著者村山氏は、これまで数度の慰霊の旅に加わったと聴くが、同じ思いにつき動かされたに違いない。戦後43年目の春、それまで頑なに秘匿され続けていた抑留日本人死亡者名簿(中に中国、朝鮮の人も)が、訪日したゴルバチョフ・ソ達大統領によって日本政府に渡された。その数3万7000人分。その後も通達と情報で合計5万6000人分とその埋葬地も完全では無いが知らされ、墓参もできるようになった。そうしてようやく公開された名簿ではあったが、ロシア語直訳のカタカナ文字の名前は分かリづらく、重複もあるという。人にとって名前は人格そのもの、一字も間違いは許されない。中国古代文学者白川静はその著書の中で「すべてのものは、名をもつことによってはじめて具体的な存在となる…名がつけられることで、その人格が確立する」と書いているが、死者の人格と尊厳を思う村山氏は、不確かな名簿を正確にし、データベースにと70歳の誕生日を機に、一念発起したという。それは、パソコンの習得から始まリ、苦闘の達続であった。一時投げ出しそうになったとき、あの松尾芭蕉の辿った北陸路を歩くことで、老骨に鞭打ったとも聴いた。著書には「戦友」ともいう夫人の支えも熱く記してある。そして10年の偉業4万6300人の漢字名簿の達成は、06年度吉川英治文化賞に輝いた。 相次いで送られてきた二冊の大著を見ていると、赫赫と燃え盛る炎の前にいるようだ。共に、シベリアとその後を生きぬいた二人の老骨の落揮は美しい。恐らく光の海にあの死者たちの幻影を見ているに違いない。この二つの著書が戦争の時代の証言として次世代の多くに読まれることを私は切に願う。 思いたって、県農業公園に在る熊本県シベリア殉難者の碑を訪ねた。銅板に刻まれた1800余の名前が、炎暑の蝉しぐれの中に、しんとしてあった。 【しんぶん赤旗】 終戦直後、ソ連軍によってシベリアに抑留された多くの日本兵。酷寒と飢餓と重労働の日々でした。「戦争を知らない世代に伝えたい」という山下静夫さん(89)。その4年間の記憶を再現した画文集『シベリア抑留1450日』(東京堂出版)を刊行しました。兵庫県明石市に訪ねました。山下さんは、1945年8月15日、満州(中国東北部)で主計軍曹として終戦を迎えます。27歳でした。9月にソ連軍の捕虜になり、シベリアの収容所を転々。その生活と労働を日録的につづった画文集は、驚くべき記憶力によるもので約600ページにも及ぶ大部です。 「戦争は残酷で愚かなものなんです。息子もその一人ですが、戦後生まれの若い人たちに伝えたかった」 そういって、今も痛む左足をさすります。シベリアの伐採作業中、切り株に強打して挫傷した膝関節を。 巨人軍の選手 冬期には零下50度にもなるシベリア。森林伐採、搬出、鉄道敷設などの強制重労働。「枕木1本に死者1人」といわれました。幕舎の中は寒く暗く、枕元が厚い氷で覆われました。そして慢性的な飢え、病気。多くの捕虜が命を落としました。 しかも、解体したはずの旧軍隊の階級が温存され、将校や下士官は下級兵土をあごで使い、食糧をピンはねしました。 画文集の絵と文は、迫真のドキュメントです。 雪中での薪取り作業中に凍死した人、幕舎でタ食中にさじを口に入れたまま死んでいる青年、製材所の丸鋸で首を切断した者…。 「明日は生きていられるか。毎夜、そんな思いに襲われました。だが一方で、こんなところで死んでたまるか、帰るまでは絶対死ねないと」 画文集の大半に自身が登場します。 商家生まれのきゃしゃな体には重労働は人一倍過酷でした。肺炎やマラリアで倒れ、生死の境をさまよいました。 プロ野球・巨人軍の水原茂選手や食堂のロシア娘マーヤとの出会いと別れ。活発だった仲間たちの演劇や歌声、川柳といった文化活動…。 山下さんはたまに、フドージニク(絵描き)の手伝いになり、喜々としてプラカードや肖像画を描きました。 電車が仕事場 画文集には、352枚のペン画が収録されています。その絵は、徹底したリアリズムです。「カメラのシャッターを切った写真のように忠実に」と心がけました。画材は、B6サイズのケント紙に黒のボールペン。14歳から独習していたというぺン画の描写は、スケールが大きく、また細密で確かです。 「シベリアを書き残しておきたい」と思い続けました。極限の環境に生きる仲間たちの姿を、美しいシベリアの大地を。 帰国して25年後の1974年、抑留体験を一気に書き上げます。その文章の挿絵をと、7年間にわたって描きためてきました。 “アトリエ”は、明石から大阪までの往復4時間の通勤電車の中でした。揺れたりして、なかなかうまくいかない。 「そのうち、揺れに低抗するからいけないんだと思い当たった。いっしょに揺れながら描きましたよ」 1週間に1、2枚仕上げるのがやっとでした。 聞こえる叫び 敗戦のショツクと異郷の地での抑留。忘れようとしても忘れられない収容所での1450日。「憎むべきは戦争、もっとも大事なものは平和」。画文集からは、山下さんの叫びが聞こえてきます。 「右派の小泉・安倍(前首相)さんと続いて、大変なことになったと思った。憲法9条を変えるなんて、もってのほか。あの戦争の悪夢を繰り返すことになる。福田さん? この人も同じでしょうねえ」 【聖教新聞】 敗戦とともに50万人とも言われる旧日本兵がシベリアに連行され、酷使された実態が、あたかも眼前の出来事のように蘇った。約400枚に及ぶペン画と日記風の短文群によって辛苦の日々を再現したのは、元主計軍曹で4年間の抑留体験者。イルクーツク州タイシェトにある強制収容所での森林伐採、鉄道建設などの過酷な労働を中心に、捕虜生活の委細が生き生きと描かれている。【出版ニュース】 〈シベリアの収容所は、私にとって、恐ろしい極寒と飢餓の地獄であったが、反面ソビエトという国、ロシア人、そして、ロシアの大自然をまぢかに見聞し、日本という国、日本人についても種々考えさせられる、スケールの大きな教室といえるものだった…〉。著者は1945年夏、当時27歳、ソ連の捕虜となり、シベリアの奥地(イルクーツク)の収容所を転々としながら、バーム鉄道の強制労働に従事。1949年秋、ナホトカ港を経て舞鶴へ帰還した。本書はその4年間、およそ1450日の生活記録。収録の350枚の抑留画は現場での体験を忠実に写す。〈悪夢が繰返される前兆さえ見えはじめている〉今日だからこそ繙いてほしい画文集である。これらの画は手記を下敷に通勤電車の往復4時間を利用し、7年間を要して描き上げたという。【図書新聞】 戦後62年特集 日本人にとってのシベリア抑留終わりなき元抑留者の悲痛な思いと現代日本の歴史的責任 一筋縄ではいかないシベリア抑留問題の難しさ シベリア強制労働補償の古傷が疼く 今年もまた、日本がアジア・太平洋戦争で、連合国に無条件降伏した「8月15日」が、巡ってくる。戦後62回も暑い夏を迎えたというのに、日本民族が有史以来初めて被った「シベリア抑留」の悲劇は、政府・与党の非人道的な対応によって、未だに抜本的な解決を見ることなく今日に至っている。日本は先進八力国(G8)首脳会議に定席を占める歴とした「文明大国」。よもやもってはならないことが罷り通るのは、戦後の「民主改革」によっても一掃できなかった、日本人の古い政治思考・意識に原因があるのではないのか? 戦後、解決が積み残されてきたシベリア抑留問題の原点を踏まえながら、その人道的な解決を図るにはどうすべきか、考えてみることにしたい。 7月としては過去最大級の台風4号が南九州を直撃、あちこちで土砂災害や風水害が相次いだ翌15日夕刻であった。 東京都千代田区の国立千鳥ヶ淵戦没者墓苑で、戦後、シベリアなどソ連各地に抑留され、不慮の死を遂げた元関東軍兵士たちを供養する慰霊祭が、盛大に執り行われた。この墓苑は、先の戦争に際して、海外で亡くなった軍人、軍属、準軍属ら約240万の戦没者のうち、政府などが外地から持ち帰りながら、遺族に渡すことができなかった遺骨35万1324柱(2007年5月現在)が祀られている国の慰霊施設。この日の夕べの法要は、「千鳥ヶ淵戦没者墓苑孟蘭盆会万燈供養」といい、真正釈迦仏舎利(釈迦の聖骨)を本尊とし、釈迦真説の阿含経を奉持する仏教教団「阿含宗」(桐山靖雄管長.大僧正)が実施した。墓苑中奥の六角堂(御霊が安置されている建造物)に向って、折り畳み式椅子による参列席が何列も設けられ、その両側には無数の万燈(迎え火)が、整然と揚げられた。法要が始まる定刻の午後6時半には、参列者は信者や遺族でいち早く満杯。その後方で立っている人々も含めると、参列者総数は約1000人にのぼった。 同宗派はこの日の法要に先立って7月8日に、ロシア極東のハバロフスク郊外に、日本政府の肝煎りで建設されたシベリア抑留犠牲者慰霊公苑で、護摩法要を行った。護摩とは尊奉する本尊の前に壇を築き、火炉を設けて護摩木(火炉に投じて燃やす木)を焚いて仏に祈願する密教独特の修法。こうして、祖国へ生きて帰還を果せなかったシベリア抑留犠牲者の御霊を、「護国の英霊」として日本に迎えて、千鳥ヶ淵墓苑で供養する法要が催されたのであった。 台風4号の余波で時折、小雨が強く降りしきる中、法要が始まって間もなく、六角堂の天空に美しい虹がかかった。それを見たこの日の法要の主催者、阿含宗関東別院のある関係者は、「60数年振りに祖国に帰ることができた『護国の英霊』の方々の歓びの現象と思われ、胸の熱くなる思いがした」との感想をもらした。 日本が先の戦争に敗れてから、早くも62年の歳月が流れた。シベリア抑留問題は敗戦直後こそ、大きな政治・社会問題となって、国民の関心を集めた。抑留者本人とその留守家族を含めると、当時の日本人の100人に1人が関り合いを持った、全国民的な大事件であったからだ。今でも懐しのメロディとして親しまれている、戦後間もなくしての大ヒット曲『異国の丘』や『岸壁の母』は、シベリアに抑留された日本人捕虜の一日も早い祖国帰還を本人や肉親が求めた悲痛な叫び声でもあった。しかし、今日では日本人の約4分の3が、戦争を実際に体験したり記憶することのない若い世代によって占められていて、シベリア抑留とは一体何のことなのか。理解に苦しむ若者が少なくないのも当然である。 そうした中で、阿含宗という一般には余り馴染みのない宗教教団が、東京のど真ん中でシベリア抑留犠牲者の慰霊法要を大々的に行ったことは、都民の耳目を驚かせるに十分であった。だが、宗派が何であれ、死者の霊を弔うことは、生きている人の務めである。第三者がとやかく言う筋合いではないだろう。問題は戦争がとっくに終っているのに、シベリアに抑留されて塗炭の苦しみを味わわされたうえ、祖国に帰還後も人道的な処遇を受けることもなく、「国に裏切られた」として、悲痛な思いに駆られている元抑留者が、今もってたくさんいることだ。彼らの胸の内には、とりわけ未だに報われないシベリア強制労働補償の古傷が痙いているのだ。あの戦争はまさに遠くなったが、元シベリア抑留者たちの「戦後」は、今もなお終ることなく続いているのである。 日本民族がかつて経験したことのないシベリア抑留の悲劇は、アジア・太平洋戦争が最終末期を迎えた1945年8月9日、それまで中立を保っていたソ連が突如、対日参戦して、日本の傀儡国家・満州国(中国東北地方)などに攻め込んだことに始まる。満州に駐屯する関東軍はソ連の侵攻を予想して、南方へ送られた兵員の穴埋めを図るため、「根こそぎ動員」によって18歳から45歳までの在満邦人男子20万人を召集して、兵員数だけは曲りなりにも70万人の頭数を揃えた。しかし、関東軍は極東ソ連軍に比べて装備が劣悪のうえ、武器弾薬が不足、根こそぎ動員で補充した新兵の練度も低く、とくに重火器や機動力に富んだソ連軍に到底太刀打ちできなかった。関東軍は怒涛のように侵攻するソ連軍に、十分な防戦をすることができずに、敗退に敗退を重ねたすえに、白旗を揚げてしまったのであった。 戦争に負けた軍隊が捕虜に取られるのは、国際法の常識である。ソ連は降伏した関東軍将兵約64万人を武装解除したのち、シベリアなどに拉致・連行して収容所にぶち込み、一定のノルマ(標準作業量)を課して強制労働に従事させた。天皇制の下で徹底した「皇民教育」を受けた日本の軍人が、こともあろうに体制が異なる社会主義国・ソ連に何十万人も連れ去られて、非人間的な労働使役に駆り立てられたことは、日本の歴史上未だかつてなかったこと。それだけに、この「異文化体験」は、日本人捕虜に精神的にも肉体的にも極めて過酷な抑留生活を強いることになった。7月に出版された山下静夫著『画文集 シベリア抑留1450日』デジプロ社)に、その一部始終が詳述されている。 山下氏は1943年に応召。満州の佳木斯駐屯の関東軍輜重兵134連隊本部詰め主計軍曹として勤務中、ソ連軍の攻撃を受け、敗戦後ソ連領内に送られ、イルクーツク州地区の収容所を転々としながら、強制労働に従事。1949年秋に、帰還した。同書は4年間にわたったこのシベリア抑留で自らが体験した捕虜生活の実態を、日録的なドキュメントとして記述。これに合わせて、あたかも記録写真のように鮮明かつ緻密に描いたペン画352枚を配した。このため、筆舌に尽し難い困難な抑留生活の模様が、一目で分かるように編集されている。 日本人捕虜にとって、いちばん過酷な強制労働は石炭採掘、森林伐採、鉄道建設などだったが、タイシェトの第40収容所に所属していた山下氏がぶつかった製材所での人身事故ほど、凄惨なものはなかった。 台車に乗せられた太い原木を挽いていた直径2メートル近い大きな丸鋸の轟音が、突然停止した直後であった。作業兵が収容所本部に駆け込んできて、「作業員が丸鋸で挽かれた」と、報告した。本部に居合わせた全員が、製材所へ向けて走った。そこで山下氏が目撃したのは、「青ざめた顔の作業兵の中心に、首のない体を抱きかかえ真っ赤な血に染って気狂いのようになって泣いている上原の姿」であった。見回すと、そのあたり一面は、血汐で真っ赤になっていて、丸鋸だけが冷たく光っていた。 事故の原因は山下氏によると、「作業員が板を挽き切ったと思い台車をバックさせたところ、原木が挽き切られておらず、板が同時にバックしたため、それに挟まれて丸鋸の上に倒れ込んだことによる」もので、「それは一秒と算えられない瞬間の出来ごと」であった。日本人捕虜に課せられた強制労働は、一瞬の油断も許されない危険な作業の連続であったのだ。 一般に厳寒、飢餓、重労働という言葉に象徴される「シベリア三重苦」に喘ぐ日本人捕虜の抑留生活は、短い者でも2〜4年、長い者となれば10余年に及んだ。揚句の果てに死者は6万2000人、負傷者は4万5000人を数え、不具廃疾者も多数にのぼった。 日本人はもっと謙虚に、自国の近現代史の見直しをする必要がある 日本国内でシベリア抑留が話題になると、いつも決って「ソ連は実にけしからん国だ」とソ連非難の大合唱が起きたものだ。無理もない。ソ連は満州などで投降後、武装解除した関東軍将兵64万人を「トウキョウ・ダモイ」(東京帰還だ)と騙して、シベリアなどに拉致・連行して、長期の抑留生活を強制しただけではない。元来、日ソ間には期限5年の日ソ中立条約(1941年4月13日締結)があって、ソ連が満州などに攻め込んだとき、この条約はまだ引き続き有効であって、失効までなお8カ月余もあった。ソ連の満州などへの侵攻は、「日ソ中立条約の一方的破棄」と言え、日本としては国際法上到底認めることはできなかった。戦後60年以上たって、日本人の間でなお対ソ非難が収まらないのは、このためである。さらに、日本が無条件降伏に当たって受諾した「ポツダム宣言吟は、その第九項で「日本軍の武装解除後連合軍の捕虜になった日本兵は、本国へ早期帰還させる」ことを謳っている。ソ連は米英などに遅れたとは言え、ポツダム宣言に調印しているので、関東軍将兵の長期にわたるシベリア抑留は、国際法でもあるポツダム宣言の明らかな違反であることは、今さら言うまでもあるまい。シベリア抑留はだれが見ても、「ソ連に非がある」と断じざるを得ないのだ。 ならば、悪いのはあくまでもソ連であっで、日本には一点の非の打ちどころもないというのか? そう厳しく問い詰められると、必ずしもそうとは断言できないところに、シベリア抑留問題が一筋縄ではいかない難しさがあることを否定できない。ではそれは、具体的にはどういうことを意味するのか? 日本国内には、戦後、シベリアなどに抑留された元日本人捕虜が書いた手記、記録、随筆などの類の書物が、私家版も含めると2000冊前後ある、と言われている。もちろん、そのすべてに目を通したわけではないが、共通するのは山下氏の画文集も含めて、次のような視点が完全に欠落していることである。つまり日本の軍隊である関東軍が、日本本土でもない異国の満州国に、なぜ駐留していたのか? 歴史に「もしも……」ということはありえないが、関東軍が満州にいなかったら、敗戦に伴うシベリア抑留も起きなかったはずだ。関東軍を満州国と関東ソ連軍の対満攻――落語の三題噺(客に3つの題を出させて、その場で一席の落語にすること)ではないが、この3つの歴史的な事象の複雑な絡み合いを解きほぐさない限り、シベリア抑留問題の本質を見誤ることになるだろう。 関東軍というのはそもそも、中国東北地方の関東州及び満州にかつて駐留していた日本陸軍諸部隊の総称である。日清・日露戦争に勝った日本が大陸侵略の一環として、1919(大正8)年に、それまで置かれていた守備隊を独立した部隊に改編・増強して発足したものだ。この関東軍に課せられた軍事的な役割は、大陸侵略の「外征軍」であると同時に、満州国支配の「植民地軍」という2つの顔を持っていて、日本の軍隊の中では最も侵略的な性格を持った軍隊であった。 関東軍に与えられた守備する責任と権限の範囲は、元来、関東州一円と南満州鉄道(満鉄)とその付属地だけであった。それ以外の地区に軍隊を出動させれば、国外に出兵するのと同じことになった。このため奉勅命令なしに勝手な軍事行動を起してはならない枠がはめられていた。だが、実際に陸軍中央の統制に背いて、関東軍は軍事的にしばしば独走したものだった。 その最たるものは、「満州事変」(1931年9月18日)という軍事謀略によって、日本の傀儡国家・満州国を建国したことであった。満州国が建国されると、「王道楽土」「民族協和」のスローガンの下に、日本から大量の開拓移民が満州に送り込まれた。先住の中国民を追い出して没収したり、安値で買い上げた耕地に、続々と入植したのだ。満州各地では当然のことながら、先祖伝来の所有地を奪われた中国農民がゲリラ化し、坑日義勇軍が組織され、日本の満州支配を武力で覆そうとした。中国農民の抵抗を警察力で取り締まれないときは、関東軍が治安出動して鎮圧した。 1937(昭和12)年7月7日。北京郊外で盧溝橋事件が突発。これが引き金となって、日中全面戦争(支那事変)が始まった。日本政府は「不拡大方針」を打ち出したが、日本の支那駐屯軍が劣勢のため、兵力を早急に増強する必要が生まれた。陸軍は関東軍から旅団規模の兵力と飛行集団の一部などを割いて、支那駐屯軍司令官の指揮下に置いた。その後もたびたび、在満部隊の一部による増援が行われ、関東軍は日中戦争拡大の一役を担った。 一方、満州国の建国は、日本とソ連の間の軍事的な緊張を激化させた。満州国は東、北、西の3つの防衛正面で、日本の潜在敵国・ソ連と総延長4000キロにわたって、直接国境を接することになった。この結果、国境紛争事件が頻発。極東ソ連軍の戦力を見くびった関東軍は、張鼓峰事件(1938年7月)に続くノモンハン事件(1939年5月〜9月)では、惨敗を喫してしまった。そして、最後に迎えた日ソ戦争(1945年8月)でも、怒涛のごとく満州に侵攻してくるソ連軍に徹底抗戦することなく、関東軍はたった一週間の戦闘で、敗北に追い込まれてしまったのであった。 太平洋戦争末期のソ連の対日参戦は、1945年2月のヤルタ会談で、スターリン・ソ連首相とルーズベルト米国大統領の談合によって取り決めた「密約」を、実行に移したものであった。明治以降大正を経て昭和に至る、日本の大陸侵略政策が敗戦によって完全に破産して、その結果が関東軍将兵の大規模なシベリア抑留につながって行ったのである。この歴史的事実に目をつぶって、ソ連の非道振りのみ非難し、日本がやたらに被害者面するのは、著しく公平を欠くことになろう。シベリア抑留は、戦前・戦中の天皇制国家・日本はもちろん、その後継国家である現代の日本もその一半の責任を負わなければならない歴史問題なのである。この点、日本人はもっと謙虚になって、自国の近現代史の見直しをする必要がある。 【教育家庭新聞】 終戦直前の昭和20年8月、ソ連との国境付近に軍曹として駐屯していた著者は、終戦後、ソ連軍の捕虜となり、シベリアへ抑留され、4年間のソ連滞在を余儀なくされた。本書は、自身の体験を後世に伝えたい、残したいという著者の強い思いが結実した大作。 日記形式で構成される記録は、ソ連が宣戦布告をした翌日の昭和20年8月9日から始まる。毎日の様子を綴る文章と、精緻な350枚のペン画が、当時の様子を圧倒的な迫力で蘇らせる。 シベリア抑留の実際を伝える貴重な資料だ。 【福井新聞】 極寒の苦難ペン画で再現 太平洋戦争後の当時のソ連によるシベリア抑留の4年間の体験を克明に記した画文集「シベリア抑留1450日」が出た。著者が帰国後7年間書き続けてさたペン画350枚に日記風の記録文が添えられ厳しい生活をよみがえらせている。 著者の山下静夫さんは十代にぺン画を学び1945年ソ連軍の捕虜となりシベリアのイルクーツクで鉄道建設をさせられた。49年に帰国。74年から7年間、通勤電軍の中で記憶をたどって記録画を描き続けた。 600ページを超えるぶ厚い本の半分以上を占めるぺン画は背景までしっかりと描かれ、敗戦後のぬかるみの長い行軍、収容所でのマイナス40度での作業、現地の人たちとの交流など抑留者の生活と心理が書かれ貴重な記録となっている。 今回の出版には小浜市出身の斎藤安弘さんがかかわった。東京の「デジプロ」という本作りの会社の編集者の斎藤さんは叔父がシベリアで亡くなったこともあり、山下さんの絵と文章を後世に伝えていかなければならないと後押しした。自費出版も覚悟したというが、東京堂出版が発売元となった。 【静岡新聞】 戦争体験記、シベリア抑留記は今もなお数多く出版されているが、本書は出色だ。克明なペン画352枚と日記体の記録文を、596ページもの大部に収めた画文集である。 大戦末期、昭和20年8月9日のソ連の満州侵攻から、24年に舞鶴港に帰リ着くまでの貴重な体験と、捕虜として強制移送された収容所での厳しい生活と労働が、記録写真のように鮮明でち密な画と、日録的に記憶をよみがえらせたドキュメントで具体的に再現されている。 終戦とともに、シベリアには60万人が抑留され、その多くが犠牲者となった。現存者は7万人程度ともいうが、戦争の悲惨さ、極寒の地での非業さが本書には如実に表れている。 「戦争、シベリア抑留の実態をありのままに」という著者の執念が、戦後7年間も通勤電車の中で数百枚のペン画を描かせ、詳細な記緑として結実した。 読みやすく資料性に富んだ一冊である。 【新潟日報】 4年余に及ぶシベリア抑留生活を、350枚の細密なペン画と日記風の手記で再現した。極寒の地で飢餓と病が襲い、戦争が終わったにもかかわらず、次々と犠牲者が増えていく。 戦争は残酷で無駄の最たるもの、と著者はいう。「その教訓を顧みることなく、悪夢が繰り返される前兆さえ見え始める昨今」、息子を含めた若い世代に、シベリアで得た教訓を伝えようとペンをとった。 決して声高に語るわけではない。淡々とした筆致に「事実を正確に記録する」との著者の思いが現れている。 |
| ご注文は |
 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-2 サンエスビル 電話 03-3511-3001 FAX 03-3511-3006 | ||
| 電話、FAX等でお申し込みください。 |